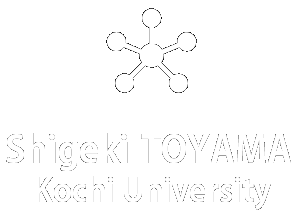
| 氏 名 | 遠山 茂樹 (とおやま しげき); TOYAMA, Shigeki |
| 所 属 | 国立大学法人高知大学 教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門 教授 (人文社会科学部人文社会科学科国際社会コース) |
| 専門分野 | 社会情報学、社会ネットワーク論、メディア論、地域情報論、コミュニティ論、社会学、など |
| 担 当授業 | メディア論、社会ネットワーク論、メディア社会論、社会学など |
| 1991年03月 | 青山学院大学国際政治経済学部国際経営学科 卒業 |
|---|---|
| 1991年04月 | 日本鉱業株式会社 入社 (1992年 日鉱共石株式会社、1993年 株式会社ジャパンエナジー) |
| 1995年06月 | 株式会社ジャパンエナジー 退社 |
| 1998年03月 | 東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻社会情報学専門分野 修士課程 修了 |
| 2001年03月 | 東京大学大学院人文社会系研究科社会文化研究専攻社会情報学専門分野 博士課程 単位取得退学 |
| 2001年04月 | 高知大学 人文学部 就任 |
| 2003年04月 | 早稲田大学総合研究機構(道空間研究所)客員研究員(~2006年03月) |
| 2015年09月 | ノースウェスタン大学(米国)客員研究員(~2016年07月) |
| 現在 | 国立大学法人高知大学 人文社会科学部 教授 |
(関係した国際学会等)
<社会情報学会:中国・四国支部>
2020年度社会情報学会中国・四国支部第2回研究発表会について [2021.02.27.終了]
researchmap (遠山茂樹 - マイページ)へのリンク
| 1 | 長田攻一・坂田正顕・千葉文夫共編著(2007a)『道空間のポリフォ
ニー』音羽書房鶴見書店 [第3章「コミュニティ形成と道空間ネットワーク」(pp.67-94.)を執筆] |
| 2 | Stillman, L. & G. Johanson eds.(2007b) Constructing
and Sharing Memory: Community Informatics, Identity and
Empowerment, Cambridge Scholars Publishing. ['The Mapping of Memories onto the Community Space' (pp.289-299)を執筆 |
| 3 | Stillman, L. , G. Johanson and R. French eds. (2009a) Communities
In Action: Papers in Community Informatics,
Cambridge Scholars Publishing ['Local Area SNS and Community Building in Japan' (pp.94-106)を執筆] |
| 4 | 高知大学人文学部「交流する社会・文化」プロジェクト編(2010)『はじめての越境社会文化論』リーブル出版 [第11章「高知における情報化の日常生活への影響:地域SNSがもたらす生活領域の”越境”についての考察」 (pp.219-241.)]を執筆 |
| 5 | 岩佐和幸・森直人・岩佐光弘編著(2015)『越境スタディーズ―人文学・社会科学の視点から』
リーブル出版 [第9章 地域情報と大学生:地域住民としての大学生の地域コミュニケーションと‘クチコミ’」(pp.199-223.)を執筆] |
| 1 |
山下興作・山本恭子・岩佐和幸・遠山茂樹著(2007)『交流する社会・文化:高知へ/高知からのまなざし』2006年度 高知
大学人文学部研究プロジェクト・研究成果報告書 [II節「情報・文化交流と地域社会:「とさはちきんねっと」とアートマネジメントを中心に」(pp.25-29.)を執筆] |
| 2 |
長田攻一、坂田正顕、関三雄、千葉文夫、坂上桂子、遠山茂樹、入江正勝ほか7名と共著(2009b)『現代都市街路空間の多元性
と 公共性』科学研究費補助金(基盤研究C)「現代都市の道の多元的な空間構成における公共性とコンフリクト」(課題番
号:19530475)]科学研究費報告書 [2.6 街路市空間における複合空間性について:”土佐の日曜市”の路上観察ビデオ映像分析による複合空間性に関する事例研究 (107-116頁)を執筆] |
| 1 |
高知大学松尾國彦基金図書刊行会編(2007)『越境する人と文化』リーブル出版(教科書等) [第6章「生活の情報化を考える:「はちきんねっと」にみる高知の情報化のあり方」(pp.119-136.)を執筆] |
| 2 |
遠山茂樹(2008)「市民生活と情報化」『LIBERATION 高知大学ラジオ公開講座読本 Vol.10 人文編』 |
| 1 |
第18回情報文化学会賞・片方善治賞 受賞(2012年10月) |
| 1 |
遠山茂樹(1998年10月)「アメリカにおけるコミュニティ・ネットワーキングについて」第13回日本社会情報学会
(JASI)大会(於:東京大学) |
| 2 |
遠山茂樹(1999年6月)「地域コミュニティにおけるユニバーサル・インターネット・サービスの取り組み:アメリカ・ミシガン
州の事例を通して」第16回情報通信学会大会(於:麗澤大学) |
| 3 |
遠山茂樹(2000年6月)「イギリスにおけるコミュニティ情報化についての考察:サウスヨークシャーの事例研究を通して」第
17回情報通信学会大会(於:電気通信大学) |
| 4 |
遠山茂樹(2001年9月)「貧困コミュニティとメディア・アート・プログラム:デジタル・デバイド問題への効果的対応策の一つ
として」第20回日本放送芸術学会大会(於:高知大学) |
| 5 |
遠山茂樹(2001年10月)「メディア・アートとコミュニティ情報化プロジェクト:シカゴのストリートレベル・ユース・メディ
アの事例研究を通して」第16回日本社会情報学会(JASI)大会(於:早稲田大学) |
| 6 |
増田祐司, 藤原博彦, 張 秉煥,
遠山茂樹(2002年11月)「知的クラスター形成支援のための地域構造」(ワークショップ「社会情報と知識経済化」の問題提起者の1人として)第7回日本社会情報学会
(JSIS)大会(於:群馬大学) |
| 7 |
遠山茂樹(2005年4月)「Community Informatics
と道空間」平成17年度情報文化学会関東支部大会(於:早稲田大学) |
| 8 |
藤原博彦, 片方善治, 増田祐司, 遠藤薫,
遠山茂樹(2005年4月)パネルディスカッション「学際研究、情報文化、または社会情報をめぐって」(パネラーとして)平成17年度情報文化学会関東支部大会(於:早稲
田大学) |
| 9 |
遠山茂樹(2006年5月)「コミュニティ開発における空間情報の活用について:萩まちじゅう博物館構想とHAGIS」平成18
年度情報文化学会関東支部大会(於:早稲田大学) |
| 10 |
遠山茂樹(2006年9月)「コミュニティ・インフォマティックスと地域空間形成」第21回日本社会情報学会(JASI)全国大
会(於:学習院大学) |
| 11 |
遠山茂樹(2006年9月)「コミュニティ・インフォマティクスにおける“場所性”の創出とWeb-GIS:まちじゅう博物館
HAGISの事例を通して」情報文化学会(JSIS)第14回全国大会(於:東京大学) |
| 12 |
増田祐司, 遠山茂樹, 藤原博彦(2006年9月)「知識基盤社会における社会情報の流通と創造:Web 2.0
の可能性」日本社会情報学会(JSIS & JASI合同)全国大会 |
| 13 |
Shigeki Toyama (2006年10月) 'The mapping of memories onto the
community space: The case of the walking navigation system by
the city of Nishinomiya', The Constructing and sharing memory:
community informatics, identity and empowerment, CIRN Prato
Conference 2006. |
| 14 |
遠山茂樹・山下興作(2007年4月)「交流する社会・文化-高知へ/高知からのまなざし-」人文学部研究プロジェクト中間報告
会(於:高知大学) |
| 15 |
遠山茂樹(2007年10月)「生活の情報化と“とさはちきんねっと”」第10回高知大学部局間合同研究発表会(於:高知大学) |
| 16 |
Shigeki Toyama (2007年11月) 'Local area SNS and community
building in Japan', Communities and Action, CIRN Prato
Conference 2007. |
| 17 |
遠山茂樹(2011年2月)「ソーシャルメディアを使った地域の社交場について」日本社会情報学会(JASI)第2回中国四国支
部研究会(於:高知市立自由民権記念館研修室) |
| 18 |
Shigeki Toyama (2016年4月) 'Egocentric Network Characteristics
and Disaster Preparedness in Rural Japan', XXXVI Sunbelt
Social Network Conference of the International Network for
Social Network Analysis (INSNA) [Poster Session] |
| 19 |
遠山茂樹(2016年9月)「災害レジリエンスにおけるパーソナル・ネットワーク特性の影響」2016年
社会情報学会(SSI)学会大会(於:札幌学院大学) |
| 20 |
遠山茂樹(2016年11月)「地域コミュニケーション行動におけるパーソナル・ネットワーク構造および社会的属性の影響につい
て―高知県下の黒潮町と奈半利町との比較分析―」情報文化学会(JSIS)第24回全国大会(於:東京大学) |
| 21 |
遠山茂樹(2017年12月)「郡部コミュニティにおける住民の防災力の規定要因についての分析
~共分散構造分析による」2017年度社会情報学会第1回中国・四国支部研究発表会(於:島根大学) |
| 22 |
遠山茂樹(2019年9月)「家庭防災とパーソナル・ネットワーク特性
~高知市家庭防災パネル調査(第1波)結果より~」2019年 社会情報学会(SSI)学会大会(於:明治大学) |
| 23 |
遠山茂樹,・北川尚(2019年11月30日)「家庭防災パネル調査
中間報告」家庭防災講演会(於:オーテピア高知図書館ホール) |
| 24 |
遠山茂樹(2020年2月)「高知市住民の社会ネットワーク構造 -高知市家庭防災パネル調査より-」2019
年度社会情報学会第2回中国・四国支部研究発表会(於:高知大学) |
| 25 |
遠山茂樹(2022年9月)「COVID-19パンデミック下の心理的ストレス反応と情報行動に関する探索的研究」2022年
社会情報学会(SSI)学会大会(於:東北大学) |
| 25 |
遠山茂樹(2022年11月)「地方都市住民のCOVID-19関連情報入手源と心身ダメージに関する探索的研究 -高知市住民
を対象とする社会調査より-」情報文化学会(JSIS)第30回全国大会(オンライン開催) |

科研費研究・基盤研究(C) 研究代表 2023-2028
<2024年度>
・安芸市家庭防災調査 回答受付は終了しました。
・香美市家庭防災調査 回答受付は終了しました。

科研費研究・基盤研究(C) 研究代表 2017-2022
災害に関する社会学的研究では、古くから戦争、革命、飢餓、ペスト(疫病)なども“災害”として扱ってきまし た。主に自然災害(特に地 震)を想定した家庭防災について調査研究を進めてきた本研究室でも、今回の新型コロナ禍を“災害”の一つと捉え、これまでの家庭防災パネ ル調査の延長として、緊急アンケート(Google Formを使用したオンライン調査)を企画しました。
緊急アンケートでは、新型コロナ禍において皆さんがどのようなことに困っていて、どのような人たちから支援を受けているのか等について
質問しています。皆さんが困っている現状を把握し、公表することで、必要な手立てへの一助となればと考えています。
今回のアンケートは、これまでの『高知市 家庭防災パネル調査』へご協力をお願いした人たち(以前に高知市選挙管理委員会作成の選挙人名
簿より無作為抽出(系統抽出法)で選出させていただいた人たち)へ、再びご協力をお願いしています。
オンライン・アンケートへの回答時間はおよそ10分間です。アンケートの回答締切は令和3年1月31日(日)までと なっています。アン ケートに入力された回答は、全て匿名で記録されます(個人が特定されるデータは収集していません)。結果はすべて数字の形で統計的に処理 します。皆様の秘密を守ることをかたくお約束しますので、ありのままをお答えくださいますようお願いいたします。
お忙しい中、大変恐縮ですが、緊急アンケートへのご協力をよろしくお願いいたします。
令和2年11月吉日
遠山茂樹
※ アンケートは令和3年2月28日(日)に回答を締め切りました。
回答にご協力いただいた皆さまには心より御礼申し上げます。
<高知市 家庭防災パネル調査>
[第1波]
高知市選挙管理委員会の許可を得た上で、選挙人名簿より1372人を抽出しました。最終的には、住所不明等を除いた1336人に対して 2018年11月に調査票を郵送しました。376通の回答を回収し、回収率は28.1%でした。
[第2波]
第1波調査で返信された372人のなかで第2波への協力許可をいただいた249人に対して調査票を郵送し、 127通の回答を回収した。回収率は51.0%でした。
[第3波]
『高知市家庭防災パネル調査』第3波は、新型コロナ禍にあたり、次年度(令和3年度)へ延期しました。
[追加:第1波]
パネル調査第1波の回答率が想定より低かったため、追加調査を企画・実行しました。高知市選挙管理委員会の許可を得た上で、新たに 700人 程度のサンプルを抽出し、最終的には721人へ調査票を郵送しました。回収した調査票は164通で、回答率は 22.7%でした。
[追加:第2波]
『高知市家庭防災パネル調査 追加調査』第2波は、新型コロナ禍にあたり、次年度(令和3年度)へ延期しました。
[特設ページ]
令和3年10月から『家庭防災パネル調査』の第3回と追加調査第2回を実施します。
今回、新たに「家庭防災パネル調査」のページを作成しました。
調査に関するご案内などを掲載しています。

科研費研究・基盤研究(C) 研究代表 2013-2017
<研究成果>
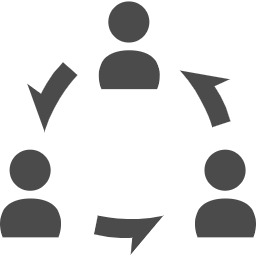
高知県内で活動していた地域SNSの研究をしていました。残念ながら、調査協力いただいた地域SNSは既にサービスを停止して います。

科研費研究・若手研究(B) 研究代表 2004-2006
<研究成果>
遠
山(2006a)
遠山(2006b)
TOYAMA(2007b)

大学院時代の研究テーマは、主にアメリカおよびイギリスにおけるコミュニティ・ネットワーク/コミュニティ・ テクノロジー・セ ンターに 関する研究でした。
<研究成果>
遠山(1997)
遠山(1998)
遠山(2000)
遠山(2000)
遠
山(2002)
遠
山(2003b)
お問い合わせは以下までお願い致します。
s-toyama(アット マーク)kochi-u.ac.jp
